(06年9月19日追記) 06年7月末に閉店しました。ご苦労さまでした。 ブログに簡単に報告あります……クリック地獄 (04年12月1日記、上の写真は10月末撮影、開店前なので暖簾が出てない) 西日暮里の竹屋食堂で、朝日新聞記者で『東京下町』(創森社)の著者、小泉信一さんに会ったのは、9月の末だった。そのとき、不二食堂の閉店を知らされた。たしか11月の何日かに、常連の落語家や芸人たちがお別れの宴をやる準備をしている、というような話もあったと思う。 その後、状況は変わって、営業を続けることになった。そのことが、朝日新聞11月30日の夕刊に載った。書いたのは、もちろん小泉信一記者である。  「下町食堂 愛され70年」「閉店…なじみ客ら止めた」という見出し。 「下町食堂 愛され70年」「閉店…なじみ客ら止めた」という見出し。店を切り盛りしてきた、青木富士子さんは67歳、夫の秀夫さん69歳。「仕事がここ数年、きつく感じられてきた。3人の子供も店を継がなかった。」「「食堂を壊してアパートにします」。閉店を知らせるビラを作った。」「閉店の話に、常連客のほとんどが反対した」「「大衆食堂を愛し、応援してくれる人がこれほどいるとは思わなかった」。悩んだ末、夫と2人でのれんを守っていくことを決めた」……という経過である。 記事下段に「大衆食堂、25年で4万店廃業」の記事がある。ここに「食文化に詳しいフリーライター遠藤哲夫さん(61)」が登場する。なんだ、おれじゃないか。 「地方から上京し、都会の片隅で生きる人たちにとって、大衆食堂は家庭のような存在だった。ファミレスから専門食店まで、今の日本の外食産業は一見華やかだが、何かを失っていないだろうか」というおれのコメントが紹介されている。 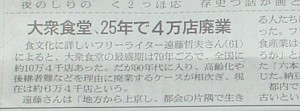 その最後に、おれのコメントではないが、おれの話や資料を参考にしたと思われる記述がある。 その最後に、おれのコメントではないが、おれの話や資料を参考にしたと思われる記述がある。「都内では、渋谷区笹塚にある「常盤食堂」が最も古いという。今年で創業82年を迎えた。」 しかし、「最も古い」という断定は難しい。それまであったさまざまな「一膳飯屋」などの飲食業から、「大衆食堂」というスタイルあるいは呼称が誕生する時代の創業であるという解釈が無難なのではないかな。つまり、大衆食堂草創期の創業であり、この時代に前後して創業した大衆食堂は、ほかにも残っている。ま、もともと「最も古い」とか「元祖」なんていうのは、大衆文化においては、さほど意味を持たない。30年50年80年、継続していることが、大切なのである。 日本の「日常文化」「生活文化」は貧しい。貧しいがゆえ大切にされず、日常より非日常性が注目され、それを中心に貧しい日常はますます貧しくなる悪循環。大衆食堂を何十年続けても、ほめられ評価されることはない。飲食業界では「最下等」の「落剥」の職業である。落ちぶれて仕方なくやるもの、板前は「落ちぶれても街の食堂だけはやるな」といわれて育つ。ときたまレトロ趣味のダシにされるていど。そういう「文化的環境」であるから、誇りを持って跡を継ごうというひとが育たなくても無理はない。 イチバン大事なのは「日常」であり「ふだんの生活」なのだ。そのことを、大衆食堂の常連たちは、よく知っている。であるから、このように常連たちが、閉店を思いとどまらせるということがあるのではないか。 そういう常連たちもまた、「大衆食堂あたりにたむろする連中」と、世間の「市民」たちの目は冷たい。恵比寿、六本木あたりのレストランや、そのコピーをウロウロすることが、もてはやされるのである。コレ、「日常文化」「生活文化」が貧しい結果である。企業のマーケティングや流行にふりまわされずに、大切なものを見つめ、自分の生活の文化を、しっかりつくりあげるべきじゃないだろうか。 「閉店騒動」のたびに何度も書いてきたが、企業が提供する華やかな飲食文化だけが文化なのではない。企業経営ではできない、個人経営家族経営だからできる、地味かもしれないが、人間交流や地域を基盤にした、よい優れた伝統が息づいている「生業文化」を、もっと大事にすべきだろう。 ともあれ、営業継続はよろこばしいことだが、お二人とも高齢である。食堂しごとは楽ではない。 ま、お札になった樋口一葉さんの記念館は、国際通りをはさんでこの不二食堂と反対側の路地裏へんなので、ついでがあったらおでかけください。 ザ大衆食│ヨッ大衆食堂│大衆食的 |
